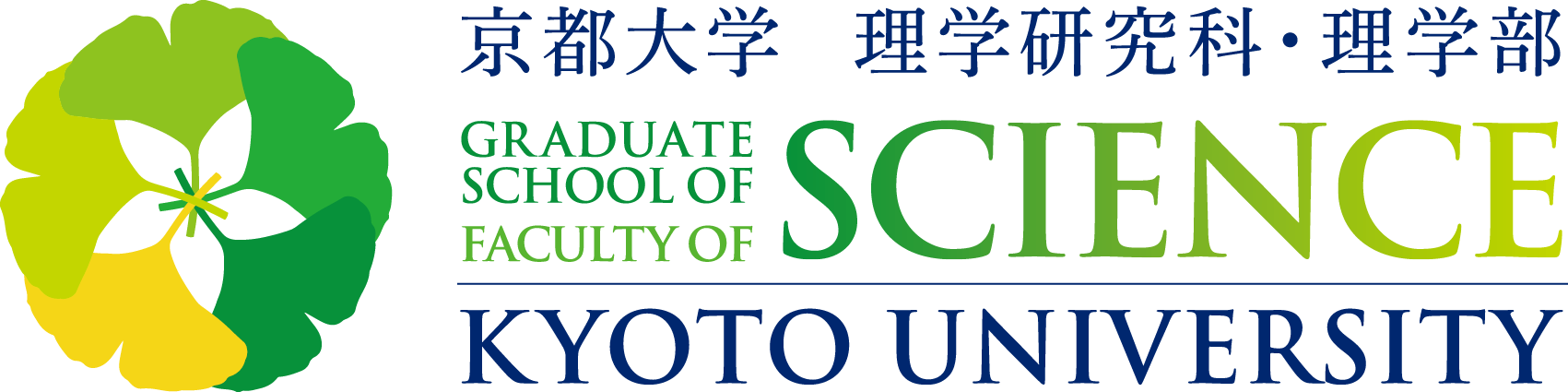物理学・宇宙物理学専攻(物理学第二分野)助教 内田 裕之

この稿の案を練っているころ、ちょうど紫金山・アトラス彗星が見ごろで、京都でも日没後の西空で長い尾が確認できたとのこと。このような大彗星の出現率は10年に1度程度らしく、私もぜひ肉眼で見たいと思っていたのだが、夕方に会議が入ったり曇天だったりでついに極大期を逃してしまった。
歴史的にこうした突発天体は「客星」と呼ばれ、平安貴族の日記にも登場したりするけれども、その中でも最も派手なイベントが、壮絶な恒星の死、超新星爆発だろう。超新星は銀河系内で100年に1度の割合で起きると考えられ、過去の例では昼間でも見えるほど明るかったという。
一体、彗星なり超新星なり、夜空に突如現れて明るく輝く客星は、昔の人々の胸を騒がせずにはおかなかった。私が研究するある超新星は西暦1006年に爆発したことが知られている。平安時代中期にあたり、藤原道長はこの客星の出現を憂慮し、天皇に祈祷を上申した。同時代の紫式部もこれを目撃したに違いない。源氏物語には、不穏な世の中の描写として「天つ空にも例に違える月日星の光見え」の記述があり、私は作者の実体験を踏まえたものと想像している。興味深いことに、戦国時代にも2度の超新星爆発があったにもかかわらず、日本には明確な文献がのこっていない。戦乱の時代の人々には、星空を見る余裕などなかったのだろうか。
現代天文学が発達したこの100年、我々の銀河系で超新星爆発はまだ起きていない。私は次に爆発が起きたときに、これを最新の観測装置で捉えたいと考えている。研究に励んでいるときにふと思い出すのは、正岡子規の短歌である。
真砂なす 数なき星の 其の中に 吾に向かひて 光る星あり
私に向かって光る星が現れることを期待しつつ、そのとき皆がのんびり星を眺められるような、平穏な世の中になっていることを祈願しつつ擱筆したい。